

3月も下旬に差しかかり、企業や組織では新体制への準備が進む時期となりましたね。
新たな配属やチーム編成が行われる中で、現場ではちょっとした緊張感や摩擦が生まれやすくなります。
そんな中、今回は「チーム内の対立」について、どのように建設的に捉え、活かしていけるかをテーマにお話ししていきます。
対立はネガティブなものじゃない
春からの新体制を迎えるにあたり、ある組織ではチームAとチームBのリーダーがぶつかるという出来事が起こりました。
こうした「方向性の違いによる対立」は決してネガティブなものではなく、
むしろ組織にとって非常にポジティブな兆候だと捉えるべき出来事なんです。
対立の多くは「相手をやっつけたい」「自分が勝ちたい」というものではなく、
「こうしたい」という理想や願望のぶつかり合いであることが多いのからです。
対立を「宝」に変えるには
では、実際に対立が起きたとき、どうすればその状況を良い方向へと持っていけるのでしょうか?
まず「お互いがどうしたいのか?」を腹を割って話すことが大切になってきます。
例えば、チームAのリーダーが「うちはこうしたい」と考えているなら、その思いをチームBのリーダーにきちんと伝える。
そしてチームBも「私たちはこういう方向を目指している」と率直に伝える。
その上で、「じゃあどうすればお互いの理想を両立できるか」を一緒に模索するのです。
このとき大切なのは、「同じやり方に統一しなければならない」という思い込みを手放すこと。
異なるアプローチでも、同じ目的地にたどり着くことは可能です。
時には、プランAとプランBを同時に進めても良いですね!
対立を恐れないカルチャーをつくること
日本では「対立は避けるもの」「できれば揉めたくない」と考える文化が根強くあります。
しかし、対立は組織が活性化するチャンスでもあります。
特に「熱意のある対立」であれば、それは組織の未来に向けた健全なエネルギー。
お互いが本気で考えている証拠であり、それをきちんと話し合い、折り合いをつけることで
チームは一段と強くなるのです。
家族も組織も本質は同じ
面白いことに、こうしたチーム内の対立構造は、家族間、特に夫婦間の衝突にもよく似ています。
お互いが家族の幸せを願って意見を主張しているのに、結果的にぶつかってしまう。
でも、根っこにある思いは同じ。
だからこそ「何のためにやっているか」という土台を確認することが大切なんです。
「建設的な衝突はむしろ歓迎すべき」
もちろん、言葉の選び方や話し方に思いやりを持つことは大前提ですが、
ぶつかること自体を恐れすぎないことが、より良いチームづくりには欠かせない要素です。
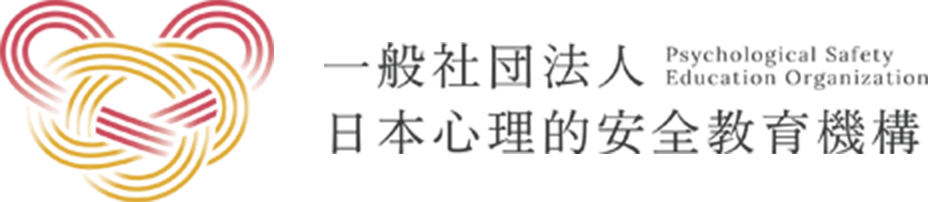




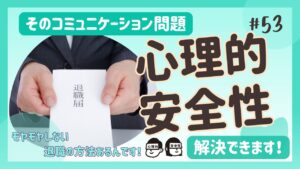
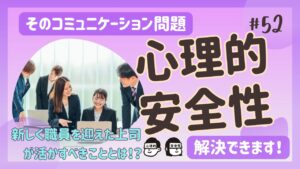

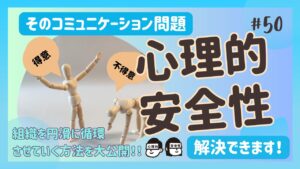

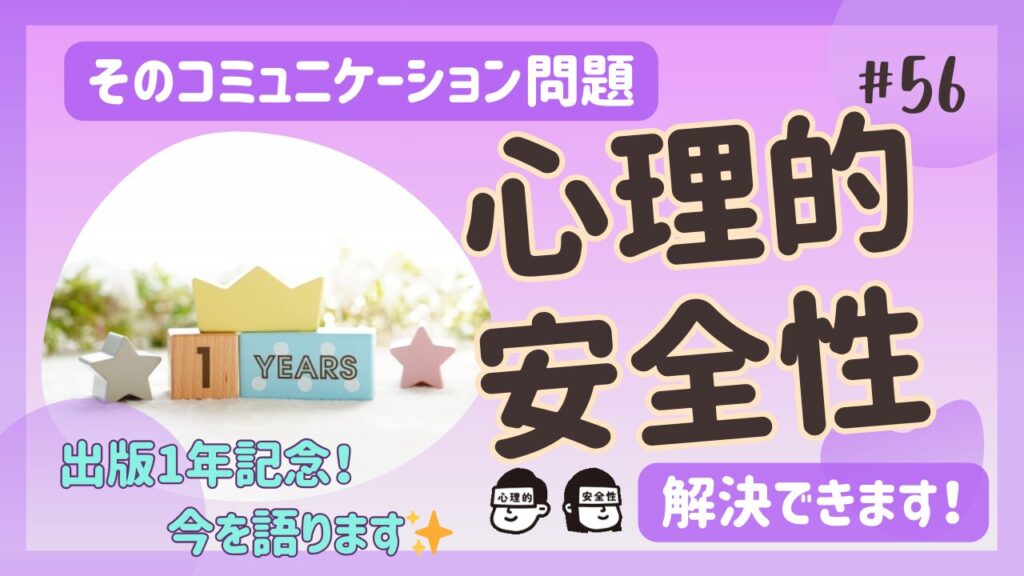




コメント